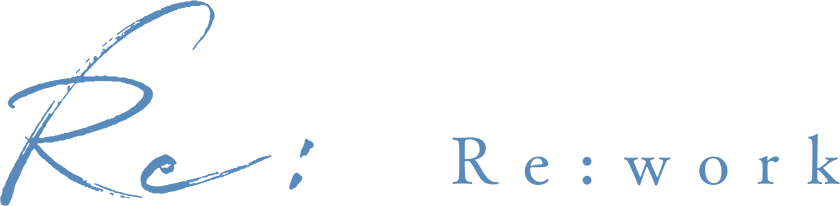育児と仕事のお役立ちコラム
2025年10月1日
子どもと過ごす時間を減らさずに、働き続けるコツ

はじめに
子育てをしながら「できるだけ子どもとの時間を大切にしたい」「でも、キャリアも続けたい」と考える女性は少なくありません。近年では共働き世帯が専業主婦世帯を大きく上回り、女性の働き方はますます多様化しています。しかし、その一方で「長時間労働によって子どもと触れ合う時間が足りない」と悩む声も多く聞かれます。
総務省「労働力調査(2024年)」によると、共働き世帯は約1,300万世帯に達し、専業主婦世帯(約500万世帯)の2倍以上。これは、女性が「働く」ことをあきらめずにキャリアを継続する時代になったことを示しています。
この記事では、データを踏まえながら「女性が働きながらも子どもと過ごす時間を確保する方法」について、具体的な工夫や考え方を解説します。
1. 女性の働き方をめぐる現状と課題
1-1. 共働き世帯の増加
厚生労働省「国民生活基礎調査(2023年)」によると、共働き世帯の割合は全世帯の65%以上。これは1980年代の約30%から大幅に伸びています。女性の社会進出や男女平等意識の高まり、また家計を支えるために夫婦共働きが一般化したことが背景です。
1-2. 女性が直面する「時間不足」の現実
OECDの調査(2023年)によれば、日本の女性は仕事に加えて家事・育児の負担が依然として大きく、1日あたりの無償労働時間は男性の約2倍。その結果、「仕事を続けたいけれど子どもと過ごす時間が十分に取れない」と感じる女性が多いのです。
内閣府「男女共同参画白書(2024年)」によると、育児期の母親の約6割が「仕事と子育ての両立に負担を感じている」と回答しています。
2. 子どもと過ごす時間を守るための工夫
2-1. 通勤時間を削減する
国土交通省「通勤実態調査」によると、首都圏の平均通勤時間は往復1時間42分。年間に換算すると約400時間以上にのぼります。
テレワークやフレックスタイムを活用すれば、この時間を子どもとのふれあいに充てられます。
2-2. 家事の効率化とアウトソース
総務省「社会生活基本調査(2021年)」によると、女性の家事時間は1日3時間以上。一方、男性は1時間未満。ここに大きな差があります。
家事分担を見直し、さらに次のような方法を取り入れることで、時間を短縮できます。
- ネットスーパーや宅配サービスで買い物時間を削減
- 食洗機・ロボット掃除機などの時短家電を導入
- 家事代行サービス(月数回でも利用可)
こうした工夫は「ママが子どもと過ごす時間」を増やす直接的な効果を持ちます。
2-3. 「完璧」を目指さない
ベネッセ教育総合研究所の調査によると、働く母親の6割以上が「家事・育児を自分でやらなければ」と考えている一方で、「時間が足りない」とストレスを感じています。
“手抜き”ではなく“合理化”と捉え、優先順位をつけることが大切です。
3. 具体的な働き方の選択肢
3-1. 会社の制度を最大限に活用
- 短時間勤務制度:小学校低学年まで利用可能な企業も増加
- フレックスタイム制度:保育園の送迎時間に合わせられる
- 在宅勤務:コロナ禍を契機に導入が進み、2024年時点で約4割の企業が実施
厚労省の調査では、制度を活用している女性ほど「子どもとの時間に満足している」割合が高いことが分かっています。
3-2. 副業・フリーランスという選択
近年、女性の在宅ワークが拡大しています。クラウドソーシング大手のランサーズによると、2024年時点で副業人口は1,200万人以上。特に子育て世代の女性が在宅ワークで収入を得るケースが増加しています。
- Webライティング
- オンライン秘書
- デザインやプログラミング
- ECショップ運営
こうした仕事は、自分のペースで調整できるため「子どもと過ごす時間を優先したい」女性にとって魅力的です。
4. 子どもと過ごす時間の“質”を高める
4-1. 量より質を意識する
ベネッセの「乳幼児の生活実態調査」によると、母親と1日1時間未満しか一緒に過ごせない子どもでも「親が子どもにしっかり向き合っている」と感じていれば情緒は安定する傾向があるそうです。
つまり、大切なのは「一緒にいる時間の濃さ」。
- 帰宅後はスマホを置き、子どもに集中する
- 寝る前の読み聞かせや会話を習慣にする
- 休日は仕事を忘れて全力で遊ぶ
4-2. 「ながら育児」から「一対一時間」へ
調査によれば、日本の母親は子どもと過ごす時間の多くを「家事をしながら」に充てています。一方で、子どもが一番うれしいのは「完全に自分だけを見てくれる時間」。
短時間でも、毎日15分程度の“一対一”を意識するだけで、子どもの安心感は大きく変わります。
5. サポートを活用する重要性
5-1. パートナーとの協力
厚労省の調査では、夫が1日2時間以上家事・育児に関わっている家庭では、妻の就業継続率が高いというデータがあります。
「一緒に子育てする」という意識を夫婦で共有することが重要です。
5-2. 地域・行政の支援
- ファミリーサポートセンター
- 一時預かり保育
- 子育て支援拠点
内閣府調査では、こうしたサービスを活用している家庭ほど「子どもと向き合う時間の質が高まった」と回答しています。
5-3. 仲間の存在
同じ働くママ同士で悩みを共有することで、精神的な余裕が生まれます。SNSやコミュニティを通じて“情報”や“共感”を得ることも、子育てと働き方を両立する大きな支えになります。
6. 心の余裕を保つために
6-1. 自分自身を大切に
子どもとの時間を増やすために無理をすると、心身に負担がかかります。
- 睡眠をしっかり確保する
- 自分の趣味やリフレッシュの時間を意識的につくる
- 「今日はこれができた」と小さな達成感を大事にする
6-2. 完璧主義を手放す
ベネッセの調査では、働く母親の多くが「家事・育児も仕事も100点を目指そうとして疲弊している」と回答しています。
“60点でOK”という気持ちでいることが、長く働き続けるためには必要です。
まとめ
女性の働き方は確実に変化しています。データが示すように、共働きは一般的になり、子育て世代の女性が働き方を柔軟に選べる環境も整いつつあります。
「子どもと過ごす時間を減らさずに働き続けるコツ」は、次のように整理できます。
- 通勤・家事の時間を削減し、子どもとの時間を確保する
- 会社の制度や在宅ワークを活用する
- 子どもとの時間は“量”より“質”を重視する
- パートナー・地域・仲間のサポートを上手に活用する
- 完璧を目指さず、自分自身の心の余裕を大切にする
これらを実践することで、子どもとの絆を深めつつ、自分らしいキャリアを築くことができます。
「女性の働き方」はひとつではありません。子どもとの時間を守りながら働き続ける姿勢こそ、これからの時代を生きるママたちのスタンダードになるでしょう。