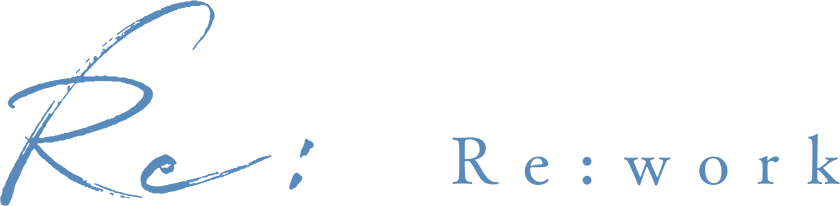育児と仕事のお役立ちコラム
2025年5月22日
共働き世帯の育児と仕事の分配方法

――マタニティライフから始まる夫婦のパートナーシップ
近年、日本では共働き世帯が増加の一途をたどっています。厚生労働省の統計によれば、子どもを持つ家庭の約7割が共働き世帯となっており、仕事と育児を両立することが現代のスタンダードになりつつあります。一方で、育児の負担がどちらか一方に偏ってしまい、夫婦関係にすれ違いが生じるケースも少なくありません。特に、出産という大きなライフイベントを迎える前後は、家庭の在り方を大きく見直すチャンスでもあります。
この記事では、「マタニティライフ」という妊娠期の時間をキーワードに、共働き世帯における育児と仕事の分担方法について考えていきます。産後の生活をスムーズにスタートさせるためには、妊娠中からの意識共有と準備が不可欠です。お互いが「家族」というチームの一員としてどう向き合うか――そこには、夫婦の絆を深めるヒントが詰まっています。
マタニティライフは準備期間
「マタニティライフ」とは、文字通り妊娠期間の生活のこと。体調の変化に伴い、これまでの日常が少しずつ変わり始めます。この時期は、母体のケアが最優先であることはもちろんですが、それと同じくらい大切なのが「これからの生活に向けての対話」です。
育児や家事の分担、仕事の継続の仕方、家計の見直しなど、出産後にいきなり直面するのではなく、マタニティライフのうちに一緒に考えておくことで、産後の混乱を最小限に抑えることができます。
例えば、「誰がどのタイミングで育休を取るか」「時短勤務にする場合の役割の調整」「夜間授乳への対応方法」など、現実的なテーマを一つひとつ言葉にすることで、夫婦の認識のズレを防げます。
分担は「公平」ではなく「納得感」
「家事育児は半分ずつやるべき」という声をよく聞きますが、実際には単純に「50:50」に分けるのは難しいことも多いです。働き方や勤務時間、職種によって体力的・精神的な余裕にも差があるため、無理に均等を目指すとどちらかに不満がたまりやすくなります。
重要なのは、「公平」よりも「納得感のある分担」です。お互いの状況を理解し合ったうえで、「この部分はあなたが得意だから任せる」「ここは私が対応するね」といった役割分担をしていくことで、自然と協力体制が整っていきます。
たとえば、料理が得意な夫が夕食を担当し、妻は洗濯と子どものお風呂を担当する、といったように、「できること」「やりたいこと」「時間的に余裕があること」を軸に分担を考えていくと、無理のないスタイルが見えてきます。
コミュニケーションがすべての基盤
共働き世帯において何よりも大切なのは、日々のコミュニケーションです。育児や仕事の分担は、1回決めたら終わりではなく、子どもの成長や家族の状況に応じて変化していくもの。だからこそ、定期的に「いまのやり方、どう?」と話し合う習慣が必要です。
特に、育児は思い通りにいかないことの連続です。寝不足、予想外の病気、突然の保育園からの呼び出し…。こうした出来事に対して、どちらか一方に負担が集中すると、ストレスが爆発しかねません。
「今日はつらかった」「ありがとう、助かったよ」といった一言を交わすだけでも、気持ちが軽くなります。「言わなくてもわかるだろう」ではなく、あえて言葉にすることが、円滑なパートナーシップの鍵です。
育児は“チーム戦”
育児に「完璧」や「正解」はありません。大切なのは、夫婦が同じ方向を見て進んでいるという感覚です。「二人で一緒に子どもを育てている」という意識があると、困難にぶつかったときにも「乗り越えられる」と思えるようになります。
もちろん、すべてを夫婦だけで背負う必要はありません。実家のサポート、地域の子育て支援、保育サービスなど、外部の力をうまく使うことも重要です。そのためにも、「頼ることは悪いことではない」という価値観を共有しておくことが必要です。
まとめ:マタニティライフから始まる“二人育児”
マタニティライフは、単なる妊娠期間ではありません。それは、これから始まる「家族の生活」の準備期間であり、夫婦が“親になる”第一歩でもあります。この時間をどう過ごすかによって、出産後の生活の質が大きく変わってきます。
共働きであることは、忙しさを意味する反面、お互いのキャリアや人生を尊重しながら支え合える関係性を築くチャンスでもあります。育児や家事を一緒に考え、悩み、工夫していく中で、夫婦の信頼はより強くなるはずです。
「ママだけが頑張る育児」ではなく、「パパとママが一緒に育てる家庭」を目指して――。夫婦というチームで、子どもと共に成長していける未来は、きっと明るく温かいものになるでしょう。