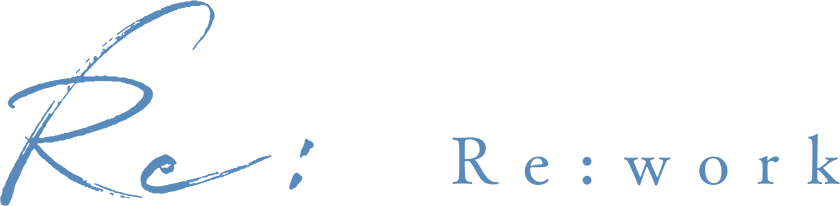育児と仕事のお役立ちコラム
2025年10月17日
リモートなど顔を併せない職場環境下での適切な管理とコミュニケーション方法(企業目線)

はじめに
新型コロナウイルスの流行をきっかけに、多くの企業でテレワークや在宅勤務が急速に普及しました。
その後もリモートワークは一時的な対応策ではなく、新しい働き方のスタンダードとして定着しつつあります。
総務省「通信利用動向調査(2024年)」によると、在宅勤務を実施する企業の割合は全体の56.5%。特に大企業では8割以上が何らかの形でテレワークを導入しています。
一方で、顔を合わせない環境では「管理の難しさ」「コミュニケーションの希薄化」「評価の不透明さ」といった課題も顕在化しています。
また、柔軟な働き方が広がることで、女性の働き方にも新しいチャンスが生まれている一方で、オンライン上での評価や連携の難しさなど、新たなハードルも存在します。
この記事では、企業目線で「リモート環境下における適切な管理とコミュニケーション方法」を整理し、特に女性社員を含む多様な働き手が活躍できる職場づくりのポイントを解説します。
1. リモートワークの現状と企業が直面する課題
1-1. リモートワーク普及の背景
テレワークはもともと働き方改革の一環として注目されていましたが、コロナ禍で一気に加速しました。
内閣府の「テレワーク実態調査(2024年)」によると、従業員のうち約35%が定常的にリモート勤務を行っていると回答。
特に子育て世代の女性や介護を担う社員にとって、通勤時間の削減や柔軟な勤務体制は大きなメリットとなっています。
1-2. 管理職が感じる難しさ
一方で、管理職の約7割が「リモート環境でのマネジメントが難しい」と回答しています(日本能率協会調べ、2024年)。
具体的な課題としては以下が挙げられます。
- 部下の業務状況が見えにくい
- コミュニケーションが減り、チームの一体感が低下
- 評価基準が曖昧になりやすい
- 孤立感・帰属意識の低下
これらの課題は、生産性の低下や離職リスクの増加にも直結するため、組織的な対策が求められています。
2. 管理のポイント:信頼をベースにした“見える化”戦略
2-1. 成果で評価するマネジメントへ転換
在宅勤務では「働いている姿」が見えないため、従来のような“時間”や“姿勢”による評価は通用しません。
企業は「成果を基準にした評価制度」に転換する必要があります。
たとえば:
- OKR(Objectives and Key Results) の導入による目標と成果の明確化
- 週次・月次での成果報告ミーティング
- プロジェクト単位でのKPI設定
成果を数値化することで、上司と部下の認識のズレを防ぎ、公平な評価が可能になります。
2-2. 進捗共有の「見える化」
リモート環境では、情報共有の遅れが大きなトラブルにつながることもあります。
Slack、Teams、Notionなどのツールを活用し、進捗やタスクをチーム全体で“見える化”することが重要です。
また、進捗確認を「監視」ではなく「支援」と位置づけることもポイント。
「状況どう?」「大丈夫?」といった声かけを、プレッシャーではなくサポートの一環として伝えることで、信頼関係を維持できます。
3. コミュニケーションの質を上げる工夫
3-1. 定例ミーティングの“目的化”
顔を合わせない環境では、意図的なコミュニケーションの設計が欠かせません。
毎日の朝会や週次ミーティングを「業務報告の場」だけでなく、「チームのつながりを保つ場」として活用します。
- 1対1の1on1ミーティングを定期的に実施
- 雑談の時間を設け、心理的距離を縮める
- カメラオン・オフのルールをチームで共有
特に女性社員や在宅ワーカーは、オフィス勤務者に比べて情報が入りにくく、孤立を感じやすいため、こうした意識的な接点づくりが欠かせません。
3-2. ノンバーバル(非言語)情報の代替手段
対面では表情や声色で相手の状態を察することができますが、オンラインではそれが難しくなります。
そのため、以下のような代替手段が有効です。
- 絵文字やリアクション機能で感情を表現
- 定期的なチャットでの「ありがとう」「お疲れさま」文化
- 社内SNSでの小さな成功共有や称賛
こうした仕組みは、心理的安全性を高め、離職防止にもつながります。
4. 女性の在宅勤務を支援する企業戦略
4-1. 柔軟な働き方がもたらす女性活躍のチャンス
内閣府の調査(2024年)では、子育て中の女性の約7割が「リモートワークを取り入れたい」と回答しています。
理由としては、
- 通勤時間の削減
- 子どもの送迎や体調不良時への対応
- 家族との時間の確保
などが挙げられます。
企業にとっても、リモート環境の整備は優秀な人材の離職防止策となり、ダイバーシティ推進にも直結します。
4-2. 評価の公平性とキャリア支援
ただし、リモート勤務を選択する女性が「評価されにくい」「昇進しにくい」と感じるケースもあります。
実際、日本労働政策研究機構の調査では、女性リモートワーカーの**約4割が「キャリア形成に不安を感じる」**と回答しています。
企業としては、
- オンライン上での成果可視化
- キャリア面談の定期実施
- 在宅勤務者にも参加できる研修・昇進機会の確保
といった公平な制度設計が必要です。
5. チームの一体感を生むコミュニケーション設計
5-1. オンラインで「雑談」をデザインする
オフィス時代のように自然発生する雑談は、リモートでは生まれにくいものです。
しかし、チームの信頼構築には雑談が欠かせません。
- 「バーチャルランチ」や「オンラインコーヒータイム」を定期的に開催
- 子育て中の社員同士のテーマ雑談(例:「朝のバタバタを乗り切るコツ」)
- 趣味共有チャンネルを設け、業務外のつながりをつくる
特に在宅勤務の女性社員にとって、こうした場は「心理的なつながり」を実感できる貴重な時間となります。
5-2. リーダーの発信がチームの空気をつくる
「上司の発言が画面越しに伝わる」ことを意識することも重要です。
感謝や称賛を積極的に言語化し、チャットでも明確に伝えることが、チーム全体のモチベーションを高めます。
6. テクノロジー活用で“距離の壁”を越える
リモートワークの質を高めるには、ツールの選定と活用方法が鍵になります。
6-1. 情報共有ツールの最適化
- Teams/Slack:部門ごとのチャンネル運用で透明性アップ
- Asana/Trello:タスク進捗の可視化
- Google Workspace/Notion:文書・ナレッジの一元管理
情報を“探す時間”を減らし、業務効率を高めることができます。
6-2. AI・分析ツールの活用
最近では、AIを活用したコミュニケーション分析や業務サポートも進んでいます。
- チャット履歴からメンバーのコンディションを可視化
- 会議の要約AIで情報共有の漏れを防止
- 勤怠データから働きすぎを検知し、健康管理につなげる
こうした仕組みを導入することで、リモートでも「人を見守るマネジメント」が可能になります。
7. 企業文化をアップデートする
リモート環境での管理・コミュニケーションの最適化は、単なる制度変更ではなく、企業文化の進化を意味します。
- 時間より成果を重視する「アウトカム文化」へ
- 管理より信頼を重んじる「共感型マネジメント」へ
- 働く場所に関係なく成長できる「フラットな組織」へ
これらを実現できる企業こそ、今後の人材獲得競争で優位に立つでしょう。
まとめ
在宅勤務やリモートワークは、もはや一過性の働き方ではなく、企業の競争力を左右する重要な要素となりました。
しかし、顔を合わせない環境では「管理」と「コミュニケーション」をどう設計するかが最大の課題です。
企業が取り組むべきポイントは以下の通りです。
- 成果ベースの評価と目標設定で信頼を構築する
- 情報の見える化とツール活用で透明性を確保する
- 定期的な1on1と雑談設計で心理的安全性を高める
- 女性を含む多様な働き手が公平に活躍できる制度を整える
- AI・デジタルツールでマネジメントを支援する
リモート環境は、単に「顔を合わせない働き方」ではなく、「信頼と成果でつながる新しい職場のかたち」です。
企業がこの変化をチャンスと捉え、柔軟で人に優しい働き方を推進することで、
女性をはじめとした多様な人材がいきいきと活躍できる未来が拓けるでしょう。