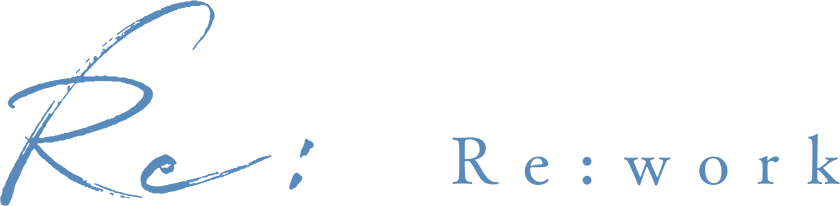育児と仕事のお役立ちコラム
2024年12月27日
ワーパパ・ワーママが活用すべき制度や助成金のご紹介

育児休業や産前産後休業などのほかにも、ワーパパ・ワーママが活用すべき仕事と子育ての両立を支援する制度や助成金が存在します。仕事と子育ての両立は、共働き家庭共通の悩みです。当記事の解説を参考に、制度を活用し、仕事と子育ての両立につなげてください。
★両立支援制度とは★
両立支援制度とは、仕事と子育ての両立を図りながら、自分らしく働くための制度全般を指す言葉です。育児休業に代表されるような公的な制度のほかにも、企業が独自に制度を設けている場合もあります。
法律の定めよりも充実した両立支援体制を設ける企業は、求職者にとって魅力的に映ります。少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少が続く我が国では、業種や企業規模を問わず、人手不足が深刻となっています。充実した両立支援制度を設けることは、人手不足解消のひとつの手段となるでしょう。また、共働き世帯への大きな助けともなります。
★両立支援等助成金★
仕事と子育ての両立を支援する助成金として、「両立支援等助成金」が存在します。同助成金には、いくつかのコースが設けられているため、コースごとに解説します。なお、「介護離職防止コース」や、「不妊治療両立支援コース」、「事業所内保育施設コース(平成28年から新規募集停止)」については、解説を割愛します。
①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
「出生時両立支援コース」は、「子育てパパ支援助成金」とも呼ばれ、文字通り子育てを行う男性従業員を対象とした制度です。男性従業員の育児休業取得率が一定以上上昇した場合や、男性が育児休業を取得しやすい環境整備を行ったうえで、出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合などに助成金が支給されます。
出生時両立支援コースには、育児休業取得者が出た場合に支給される第1種と、育児休業取得率が上昇した場合に支給される第2種の2種類が存在します。支給額は、第1種が20万円(1人目)、第2種が20万円から60万円(プラチナくるみん取得による加算あり)です。
②育児休業等支援コース
「育児休業等支援コース」では、「育休復帰支援プラン」を策定したうえで、育児休業の円滑な取得や職場復帰の取組みを行った場合に助成金が支給されます。育休復帰支援プランとは、従業員の育児休業の取得や職場復帰を円滑に進めるために、育児休業取得者ごとに事業主が作成する実施計画です。計画には、引き継ぎ情報や休業中の職場情報などを盛り込むことが求められます。
育児休業等支援コースでは、育児休業取得時と職場復帰時に助成金が支給されます。支給額は、双方とも30万円です。
③育休中等業務代替支援コース
自分が育児休業を取得したら、人手不足になって会社に迷惑が掛かるかも知れないと思い、取得を躊躇う方もいます。そのような場合には、「育休中等業務代替支援コース」が活用可能です。同コースでは、育児休業取得者の業務を代替する従業員や、育児のための短時間勤務者の業務を代替する従業員に手当を支給した場合に助成金が支給されます。また、育児休業取得者の代替として、新規雇用を行った場合(派遣の受け入れ含む)にも支給対象となります。
育児休業取得者の業務を代替する従業員に、手当等を支給した場合には、以下の1、2の合計額が支給されます。
- 業務体制整備経費:5万円
- 業務代替手当:支給した手当総額の4分の3を助成
育児のための短時間勤務者の業務を代替する従業員に、手当等を支給した場合には、以下の1、2の合計額が支給されます。
- 業務体制整備経費:2万円
- 業務代替手当:支給した手当総額の4分の3を助成
育児休業取得者の代替として、新規雇用を行った場合には、業務を代替した期間に応じて、以下の金額が支給されます。
7日以上14日未満 :9万円 (11万円)
14日以上1か月未満 :13.5万円(16.5万円)
1か月以上3か月未満:27万円 (33万円)
3か月以上6か月未満:45万円 (55万円)
6か月以上 :67.5万円(82.5万円)
※()内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額
なお、育児休業取得者や短時間勤務者が有期雇用であった場合には、上記額に10万円が加算されます。
④柔軟な働き方選択制度等支援コース
「柔軟な働き方選択制度等支援コース」では、育児を行う従業員のために、フレックスタイムやテレワーク、時差出勤などの柔軟な働き方を導入した場合に助成金が支給されます。導入した制度の数に応じて、支給額が変動し、2つの場合は20万円、3つ以上導入した場合には、25万円が支給されます。
導入対象となる柔軟な働き方は、以下の通りです。
- フレックスタイム制度
- 時差出勤制度
- テレワーク
- 短時間勤務制度
- 保育サービスの手配と費用補助
- 子どもの養育を容易にするための休暇制度
- 法定を上回る子の看護休暇制度
★育児休業終了後の支援制度★
育児休業が終了しても子育ては続きます。そのため、国は様々な制度を用意して、仕事と子育ての両立の支援を行っています。
①短時間勤務制度
3歳未満の子どもを育てる従業員が希望する場合、企業は原則として所定労働時間を1日6時間に短縮しなければなりません。現在は、3歳未満の子どもを育てる従業員が対象ですが、2025年4月からは、小学校就学前まで対象範囲が拡大されます。
②所定外労働の制限
3歳未満の子どもを育てる従業員が請求した場合、所定労働時間を超えて労働を行わせてはなりません。所定外労働の制限であるため、法定内残業も対象となります。なお、短時間勤務制度と同様に、所定外労働の制限も2025年4月から、小学校就学前まで対象範囲が拡大されます。
③時間外労働の制限
企業は、小学校就学前の子どもを育てる従業員が請求した場合、1か月について24時間、1年においては150時間を超えて、法定労働時間を超える時間外労働を行わせてはなりません。
④深夜業の制限
小学校就学前の子どもを育てる従業員の請求があった場合、企業はその従業員を深夜の時間帯に労働させることが禁止されます。対象となる深夜帯とは、午後10時から翌午前5時までを指します。
⑤育児時間
企業は、1歳未満の子どもを育てる女性従業員が請求した場合、休憩時間を除いて1日2回(労働時間4時間以内の場合は1回)各々少なくとも30分の育児時間を与えなくてはなりません。この育児時間を有給とするか無給とするかは企業によって異なります。
⑥子の看護休暇
小学校就学前の子どもを育てる従業員は、その申し出によって、1年に5日(対象となる子どもが2人以上の場合は10日)を限度とする休暇を取得することが可能です。子どもの怪我や病気の世話、または予防接種などに利用できる制度です。この休暇は有給休暇とは別に付与されますが、有給とする無給とするかは企業の自由な判断となります。
2025年4月からは、入園式などでも休暇を利用できるようになり、対象となる子どもの範囲も小学校3年生修了まで拡大されます。
★企業独自の取り組み★
企業によっては、法定を上回る両立支援制度を設けている場合もあります。企業の事例を紹介するため、自社に取り入れる際の参考としてください。
ソフトバンクでは、第1子5万円から第5子500万円までの「出産祝金」を従業員に支給しています。また、子の看護休暇を法定の5日を上回る10日まで認めるだけでなく、看護休暇とは別に年10日まで取得可能な「キッズ休暇」を設け、従業員の子育て支援しています。
キューピーでは、法定を上回る育児休業制度を設けるだけでなく、所定外労働や時間外労働、深夜業の制限を小学校4年生まで拡大しています。また、育児休業復帰者へのセミナーを開催し、スムーズな職場復帰にも取り組んでいます。男性従業員を対象とした離乳食教室も開催しており、食品を扱う同社らしさが表れた取り組みといえるでしょう。

両立支援制度や助成金を活用しよう
仕事と子育ての両立を支援する制度は、国が実施する公的なものから私企業が提供するものまで様々な種類があります。当記事の解説を参考に、自分が利用可能な制度を把握し、子育てと仕事の両立を図りましょう。
監修:社会保険労務士 涌井好文