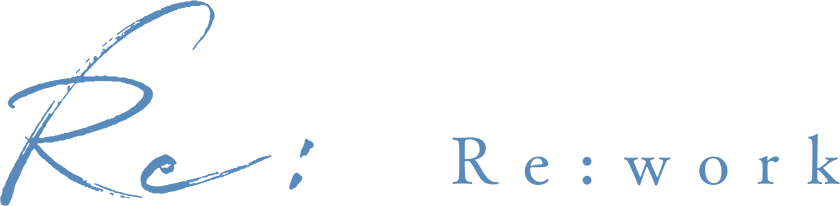育児と仕事のお役立ちコラム
2025年7月24日
夫に頼みやすい家事・頼みにくい家事

― 転職・仕事復帰をきっかけに見えてきた夫婦の家事シェアのリアル ―
仕事復帰と家庭の再編成
出産や育児を機に一度仕事を離れた女性が、いざ再び社会に戻ろうとするとき、大きな壁となるのが「家事・育児の分担問題」です。特に、転職や仕事復帰のタイミングは、家族の生活スタイル全体を見直すチャンスである一方で、「家事をどう分けるか」という課題に直面することも多いもの。
「夫に頼める家事」と「頼みにくい家事」。これは、実際に仕事を再開してから明確になることが多く、また家庭ごとにその答えは異なります。しかし多くのワーキングマザーたちが共通して抱えるジレンマには、一定の傾向があります。
本稿では、実際の事例やアンケート結果などを交えながら、「夫に頼みやすい家事・頼みにくい家事」の背景や理由を紐解き、仕事と家庭を両立する上でのヒントを探っていきます。
頼みやすい家事とは?
1. 「機械任せ」系の家事(洗濯機・食洗機・ルンバの起動)
夫に頼みやすい家事の代表格といえば、「ボタンを押せば済む系」の家事です。
- 洗濯機を回す
- 食洗機をセットする
- 掃除ロボットを動かす
これらは、手順が明確で機械に任せられる部分が多いため、夫も「やっている感」を得やすく、妻も任せやすい傾向があります。
また、家電の進化もあって「正解」が一つに定まっているため、やり方に個人差が出にくく、頼む側としてもストレスが少ないのです。
2. 「目に見える成果がある」家事(ゴミ出し・買い物)
ゴミ出しや週末の買い出しも、夫に頼みやすい家事です。これらは「終わったかどうか」が一目でわかるため、成果がはっきりしていて、達成感も得られやすい家事です。
また、「外に出る」という行動も含まれるので、夫にとっても気分転換になりやすい点がポイントです。
3. 「自分のペースでできる」家事(風呂掃除・庭仕事)
時間に追われず、自分のタイミングでできる家事も頼みやすい部類です。
「風呂掃除」や「庭の草取り」など、比較的一人で黙々とできる家事は、夫が「自分の作業」として捉えやすく、ルーティンになりやすい特徴があります。
頼みにくい家事とは?
1. 「細かい判断が求められる」家事(献立・調理・子どもの持ち物準備)
一方で、妻が「頼みにくい」と感じる家事には、「思考」と「判断」が求められるものが多いです。
例えば、夕食の献立を考えて調理する、子どもの給食袋や連絡帳をチェックするなどは、家庭内の事情や子どもの状態を把握していないと難しいもの。
また、「この調味料はどこ?」「アレルギーは?」など、細かいことをいちいち聞かれるのがストレスになり、「もういいや、自分でやろう」となってしまうケースも多いです。
2. 「段取りが必要な」家事(家族全員のスケジューリング・イベント準備)
家族全体を見渡してのスケジューリングや行事準備も、頼みにくい領域です。
たとえば、
- 運動会の準備
- 誕生日の計画
- 習い事の送り迎え
これらには、複数人の予定を調整したり、先を見越して準備したりといった「段取り力」が求められます。
夫に悪気はなくとも、「そこまで把握してない」「言ってくれればやるけど…」というスタンスになりがちで、妻が「いちいち説明するのが面倒」と感じてしまう原因になります。
3. 「日常の中に埋もれている」家事(名もなき家事)
「頼みにくい」と感じる最大の理由は、そもそもその家事が夫の目に見えていないことです。
- トイレットペーパーの補充
- 食品の在庫チェックと補充
- 保育園の連絡帳記入
- 洗濯物の取り込み→たたむ→しまう流れ
こうした“名もなき家事”は、「家事としてカウントされていない」ことが多く、夫にとってもその存在すら意識されていないケースもあります。
頼むにも、「それって誰かがやってることなんだよ」と説明しなければならず、精神的な負担も伴います。
「頼みにくさ」の正体とは?
では、なぜ家事には「頼みやすさ」「頼みにくさ」があるのでしょうか。
その理由には、次のような要素が複雑に絡み合っています。
- 可視化できるかどうか
成果が目に見える家事ほど、頼みやすい傾向があります。 - 正解が明確かどうか
工程や手順が標準化されていれば、夫も「ミスをしにくい」と安心できます。 - 責任の所在がはっきりしているか
「自分がやるべき」と認識できるかどうかも重要。曖昧だと「やらなくていい」と思われがちです。 - 夫婦間の情報格差
妻の方が圧倒的に家庭の情報を持っている場合、夫が関与しづらくなります。
転職・仕事復帰がもたらす意識変化
転職や仕事復帰のタイミングは、夫婦にとって家事分担を見直す絶好のチャンスです。
この時期は、「今まで当たり前だったことが通用しない」という小さな混乱が起きがち。しかし、それがかえって家事の属人化を見直す機会にもなります。
「これまで私が全部やってたけど、そろそろ分担を…」
「夫は料理はしないと思っていたけど、意外とハマっている」
「子どもの送り迎えは、夫の方が向いてるかも」
このように、新しい働き方に合わせて家事の役割を柔軟に見直すことで、夫婦のパートナーシップは一層深まります。
ポジティブに締めくくる:家事は「頼むこと」からはじまる
家事は、お願いする側も、される側も、最初はぎこちないものです。
特に、長年「家のことは妻がやるもの」という空気の中で過ごしてきた夫にとっては、急に全てを任されるのは負担に感じることもあるでしょう。
だからこそ、最初の一歩は「完璧を求めないこと」。「やってくれてありがとう」と声をかけること。そして、「何が苦手か」より「何が得意か」に目を向けることが大切です。
頼みやすい家事から少しずつお願いし、頼みにくい家事も「一緒にやってみよう」と取り組んでいく中で、夫婦の家事シェアは確実に変化していきます。
転職や仕事復帰は、生活を整え直す大きな転機。だからこそ、家事という名の「見えないチームワーク」を再構築するチャンスでもあるのです。
そして何より、「家事をシェアすること」は、夫婦が本当の意味で“共に暮らす”ための一歩でもあります。